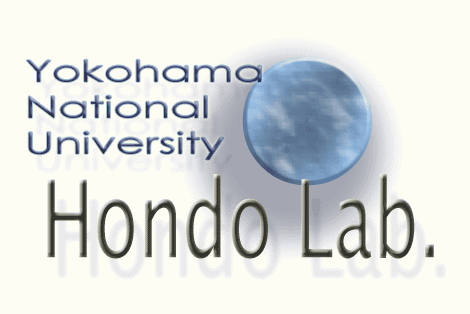2007年度 博士課程前期 修了生
田宮 麻友美
修了生からのメッセージ

fig.5 田宮さんとお子さんの素敵な2ショット
1.修士課程進学のきっかけ
本藤研の最初の修士学生として、社会人枠で環境情報学府に入学しました。当時は、循環型社会の構築という領域で、使用済み製品のリサイクルシステムの企画・
構築支援コンサルティング、政策調査などにリサーチャーとして携わっていました。
国内外の環境政策はその頃、公害問題に端を発する出口規制から、リサイクルシステムや有害廃棄物管理・マテリアルフロー管理などトータルな対策へ、
さらに戦略的な経済的手法へと進化していて、とてもおもしろく仕事に打ち込んでいました。ですが、行政・事業者に近い立場で環境政策に関わる中で、
環境問題に対する一般的な感覚との距離を感じることが多々ありました。たとえ環境改善効果が得られていても一般的には伝わりにくいし、
リスクに対する偏った理解も流通しやすいという場面をよく目にしました。また、地球温暖化問題になるとスケールが大きいために身近な感覚からかけ離れ、
何が合理的な対策か判断しにくくなり、有効な解決策の共通理解も得にくいということもありました。全体の評価、わかりやすい伝え方のツール、
という点で、LCAに興味を持っていました。
2.在学中の研究テーマと経験
研究テーマとした産業連関表を用いた揮発性有機化合物の排出に関するLCIは、時間をかけて数字と向き合いながら全体を俯瞰し、問いを深く掘り下げるという、貴重な経験でした。
統計や数値指標を扱い、仮説に基づいて推計し、その妥当性を評価するという経験はそれまでありませんでした。数字の根拠となる統計と向き合うことは、最も苦手なことでしたし、
産業連関表のデータの扱いは単調で孤独な作業になりがちで、モチベーションを保つのにはとても苦しみました。ですが、手を動かしてはじめて、統計がどういう積み上げをもとに
構成されているかという基礎の基礎となる知識がわかりましたし、推計をどう活用し、伝えるかというところも、この理解があって初めて応用が利くことだと実感しました。
修士は基礎演習と向き合う時期だったと思います。
本藤研には、推計を通してテーマに向き合っている人も、現場的なアプローチで社会的共通資本や環境教育に向き合っている人もいましたし、
社会人学生の方が毎年在籍しているのも特徴でした。所属する方の研究テーマとバックグラウンドが幅広いので、多角的な視野で環境・エネルギー問題に向き合うことができました。
在籍中に研究室メンバーからいただいた視点は今も役立っています。それぞれに刺激を与え合い、研究と社会の接点を見つめながら成長できるネットワークが本藤研には積み上がっている
のではないでしょうか。時間を共有した卒業生となら、久しぶりに話をしてもすぐに根底の部分が理解しあえるのではないかと思います。
それは、大学院を通じて問いと対峙する経験、深い知とともに、とても貴重な財産のはずです。
3.社会人学生としての経験から
社会人枠を検討されている方は、研究時間をどのくらい確保できるか、身近な方の理解が得られるかという点を考えておくことも重要かと思います。
私は在籍中に結婚、出産とライフイベントが重なり、子供をいろんな方に代わるがわる見てもらいながら修論を書くことになりました。
長男と一緒に参加した追い出しコンパで、研究室のみなさんが優しい眼差しを向けてくださったことが大変に思い出深いです。
ただ、育休復帰後に学会発表をする本藤先生との約束が果たせなかったというキャパシティ不足でふがいないこともありました。
(今は学会発表は必須かも・・・)忍耐強く指導くださった先生、家族の協力に感謝しています。
4.ひとこと
進学前は仕事が楽しかったものの、「次世代のためと言いながら、意思決定に若い人も女性もいない、おじさんばかりが幅を利かせている循環型社会ってどうなの?」と、
もやもやとしていました(言い過ぎかもしれないのですが)。これは日本社会の構造ですよね。新卒で社会に出る方は様々な場面で感じるかもしれません。
いま私は、出身地である秋田に拠点を移し、循環型社会を形成するためにできる市民とのアプローチを、とにかく若い人と、わかりやすく、を前提に模索しているのですが、
大学院レベルの知を実践に落としていく人材が地方で必要とされていることを痛感しています。おそらく各地でそういう人材ニーズがあります。ぜひ修士・博士での経験を通じて、
新しい活躍のフィールドを拓いていくことにも目を向けていただきたいなと思います。
-2012年5月21日 掲載-