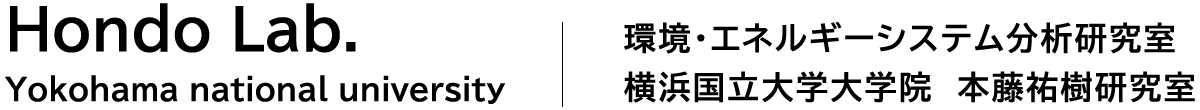2008年に修了した山田です。箇条書きにてお話しします。
1.進学動機や背景
学部の時代は理工学部で工学全般を学んでいました。 大学院進学を考える中で、その中でもエネルギーや資源を今後有効に開発・消費していくための視点に興味がわき、本藤研究室の門を叩くに至りました。 結果として、工学の分野から学際的な領域の代表格である環境分野に進んだことになりますが、特に違和感は感じませんでした。 入ってみれば、同時期に進学してきたメンバー等、文理を超えて多様な背景を持っており、それがよい刺激になったように思います。
2.研究テーマ
製品のLCAデータや社会全体での普及量や普及速度を考慮して、環境負荷を世の中全体で削減していくための意思決定ができないか、 といったテーマに基づき「寿命分布を考慮した製品最適導入計画モデル」のモデル開発や、開発したモデルで自動車の普及に関する事例分析を行っていました。
(参考として、修了後に投稿した論文を載せておきます。)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjser/30/1/30_9/_article/-char/ja
3.二年間の生活
振り返ってみると、2年間の修士の期間はとても短かったように思います。 1年目の前半では、講義を受講し手法論を学び、先行研究を調べたりします。下半期には研究の方向が固まってくる一方で、就職活動もはじまります。 定期的に回ってくるゼミ発表を前に夜を徹することもしばしばありました。2年目は研究が本番に入り、データ集めやモデル作成、計算等に没頭しました。 この時期は趣味にも研究にも時間の使い方が最も自由で、しんどい時期もありましたが楽しみながら過ごせたと思っています。かなり研究室に入り浸りました。
4.学べること
ゼミでは、背景の異なる学生、目的意識の高い社会人学生と議論をするので、随分と揉まれました。皆さん話題が豊富で個性的です。 この多様性が、学際的な分野の研究室の強みでしょう。一方で、道具としての手法やシステム思考などは、基本として勉強することになります。 そして、修士論文を一本書き上げる作業は、貴重な体験です。社会に出てからも、学んだ事柄を応用する機会によく出会います。
5.ひとこと
修了しても、たまに顔を出したくなるような研究室です。