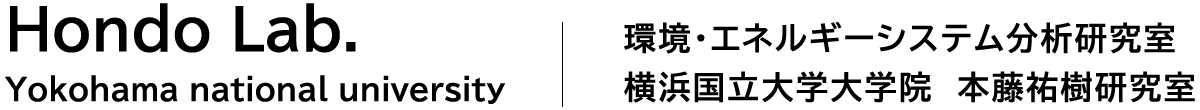私は入学前、高専の本科そして専攻科で主に情報工学(プログラミングや簡単な数値解析)を学んでいました。 私の場合修士課程に進むことを決めた理由は、これまでの知識を用いて(用いることができなければ足りないものを学びながら)、 新しい領域でこれまでとは違った新しいことをやりながら、自分の価値観や世界観を広げて成長する二年間を過ごしたいと思ったためでした。
進学について考える中で、当時はまだ漠然とした興味でしたが、キーワードとして「複合領域」「環境」「情報」を手掛かりに本藤研究室と出会うことができました。 そうして出会えた本藤研究室は、私にとって前述の目的を達成するのに絶好の場であったと思っています。
同期や先輩、バックグラウンド、年代の全く異なる各分野で活躍される個性的な社会人博士課程の皆様、そして本藤先生が周りにいる環境。 異なるバックグラウンド同士だからこそ、素直に言い合える活発なゼミと、分野を超えた情報交換は、私のもといた高専という環境では経験できるものではなく、 毎日が非常に有意義でしたし、研究以外のたとえば就職活動にしてみても、自分の人生を本気で考えさせられるアドバイスをいただきました。 HPのメンバーを見ていただければわかるように非常に個性的なメンバーだらけのすごい研究室だなと思っています。
修士研究に関しては、私は「ライフサイクル思考に基づいた環境教育用ソフトウェアの開発」というテーマに挑戦しました。 環境問題を自身の生活とつながっているのだということを実感してもらうための本ソフトウェアは、中高生を対象としていましたので、高校の先生方、 生徒さんたちのご協力なくして開発が進むものではありませんでした。そしてソフトウェアの限られた授業時間の中で効果を上げるための仕掛け、 使い方を即理解してもらえるための工夫…始める当初からは想像できない、いろいろなアイディアをゼミの中での意見をいただいた中から取り込み、 LCA、教育心理学、情報分野と幅広い文献をレビューして展開の方法を模索していきました。
ソフトウェア開発は苦戦しながらも進みましたが、一方でそれを一つの論文にするという大変さはソフト作り以上に難しいものでした。 本藤先生のご指導やゼミの中でのディスカッションで生まれたアイディアや課題を解決しながら徐々に積み上げて、どうにか修士論文を書き上げることができました。
新しい領域に挑戦して、自分の力でソフトウェアと修士論文を形にできたことは、納得いく2年間を過ごした証であったと思います。
研究に行き詰まり苦しい時もありましたが、それでも毎日研究室に行くのが楽しみで、本当に楽しい2年間を過ごすことができたと思います。 本藤研究室での2年間のおかげで、入学前から世界観や価値観は大きく広がり、入学前では絶対に描くことのなかった道を自ら見つけ出すことができ、今はその道を歩き始めました。